神田明神[神田神社]
(春秋の彼岸の中日に一番近い戌の日に、この摂社・末社の“石鳥居”をくぐってお参りすると、痛風・ボケ封じになるそうな)
みどころ満載な神田神社で一番気になる場所…
そもそもお稲荷さんに一番心動かされてしまうのだけど、神田神社社殿の裏、駐車場(藤棚が屋根になってる場所)の一角に集められた神狐さんたちと小さな祠。特に解説もなにもなく、気付く人もあまりいなさそぉで、ちょっと寂しげ。
籠祖神社が“合祀殿”として建て替えられてしまったのはちょっと寂しいけど、関東大震災・戦災で被害を受けてきた神田神社だけに、未然に“崩壊”を防ごうとするのは当たり前なのかも…なんてことを考えたりもしつつ、気軽に立ち寄れる雰囲気で、結構好きなのだ。(2013年7月撮影)
「正式名称・神田神社、東京都心108町会の総氏神様で、神田・日本橋・秋葉原・大手丸の内、そして東京の食を支える市場の発祥地の氏神様として、青果市場・魚市場の人々からもあつく崇敬されております。縁結び、商売繁盛、社運隆昌、除災厄除、病気平癒など数多くのご神徳をお持ちの神々です。
当社は、天平2年(730)のご創建で、江戸東京の中で最も歴史ある神社のひとつです。はじめは現在の千代田区大手町・将門塚周辺に鎮座していましたが、徳川家康公が江戸に幕府を開き江戸城が拡張された時、江戸城から表鬼門にあたる現在の地へ遷座いたしました。
それ以降、江戸時代を通じて「江戸総鎮守」として幕府から江戸庶民にいたるまで多くの人々の崇敬を受けました。さらに、明治に入り、准勅祭社・東京府社に烈格し皇居・東京の守護神と仰がれ、明治天皇も親しくご参拝になられました。
境内には、日本初の本格的な鉄骨鉄筋コンクリート・総漆朱塗造の御社殿(国指定登録文化財)や、総檜造の随神門、神札授与所・参拝者待合室・休憩所を兼ねた鳳凰殿、明神会館・資料館・石造日本一の大きさを誇るだいこく様尊像・えびす様尊像・江戸国学発祥の地碑・銭形平次の碑などがございます。縁結びのご神徳から神前結婚式も多く行われております。
当社の祭礼・神田祭は二年に一度執り行われ、江戸時代には江戸城内に入り徳川将軍が上覧したため、御用祭とも天下祭とも呼ばれました。また日本三大祭、江戸三大祭のひとつにも数えられております。
現在は鳳輦・神輿をはじめとする江戸時代さながらの祭礼行列が、神田・日本橋・秋葉原・大手丸の内の広大な氏子108町会を巡行する「神幸祭」と、氏子の町神輿約200基が町を練り歩き、神社へ迫力ある宮入をする「神輿宮入」を中心に賑やかに行われております。 平成19年春 神田神社社務所」神門脇由緒書きより
「社伝によると天平2年(730)、武蔵国豊島郡柴崎村(現・千代田区大手町)に創建されました。延慶2年(1309)、東国の英雄で庶民たちに仰がれた平将門公が合祀され、太田道灌・北条氏綱といった名立たる武将によって手厚く崇敬されました。
慶長5年の関ヶ原の戦いで、当社では徳川家康公の戦勝祈願をし御守りを授与したところ見事に勝利を得ました。これ以降、家康公の合戦勝利に因み縁起の御守り『勝守(かちまもり)』を授与するようになり、現在でも多くの参拝者に授与しております。江戸幕府が開かれると幕府の深く尊崇するところとなり、元和2年(1616)に江戸城の表鬼門にあたる現在の地に遷座し幕府により社殿が造営されました。江戸時代を通じて江戸総鎮守として歴代の将軍はもとより江戸の庶民たちにも崇敬されました。
明治時代に入り東京・皇城の守護神として准勅祭社・東京府社に定められ、明治7年(1874)に明治天皇が親しく御参拝になりました。大正時代、関東大震災による社殿焼失後、昭和9年に氏子崇敬者の浄財により画期的な権現造の鉄骨鉄筋コンクリート・総漆塗の社殿が造営されました。
昭和20年、東京大空襲が神田・日本橋界隈を直撃しましたが、社殿はわずかな損傷のみで戦災を耐えぬき戦災で苦しむ人々に勇気と希望を与えました。
戦後、随神門などの建造物などが再建され江戸時代にも劣らぬ江戸東京を代表する神社としての景観を整えるにいたりました。さらに平成7年より“平成の御造替事業”として社殿等の塗替・修復及び資料館の造営等が大規模に行われ、平成17年には境内の整備事業が実施され、鳳凰殿や祖霊社などが新たに造営されました。」境内由緒書きより
《境内案内》境内案内板より
社殿:国の登録有形文化財。昭和9年竣功。権現造・鉄骨鉄筋コンクリート・総漆朱塗の社殿。
随神門:昭和51年に建立。総檜・入母屋造。各所に「因幡の白兎」の神話や四神、平将門公ゆかりの繋ぎ馬の彫刻がちりばめられている。
鳳凰殿:平成17年に竣功。御屋根の両端に幸福を呼ぶ瑞鳥・鳳凰を奉安。神札授与所・参拝者待合室・休憩所を兼ねた建物。
明神会館:昭和40年に完成。社殿にて神前結婚式をあげた新郎新婦の披露宴会場として連日賑わい、また各種会議・宴席の場・催し物会場としても利用されている。
資料館:平成8年に完成。江戸文化や神田祭を伝える貴重な資料の数々が展示されている。文化財「神田明神祭礼絵巻」や山車人形などを所蔵。
だいこく様ご尊像:石造では日本一の大きさを誇る。昭和51年建立。
えびす様ご尊像:波間より魚たちとともにいらっしゃる姿をしためずらしい像。平成17年建立。
記念碑:獅子山(区内に残る数少ない江戸期の石造物の一つであり、当時の庶民の信仰を知る上で貴重な資料である。『武江年表』には「文久2年(1862)11月両替屋仲間より神田社前へ、岩石を積み、石にて刻みし獅子の子落としの作り物を納む」とあり、江戸時代でも幕末期に製作されたと考えられる。神社境内の獅子山に据えられていたが、大正12年(1923)の関東大震災により獅子山自体は崩壊した。その際、子獅子は、紛失したものの、親獅子二頭は、保存され、再建された獅子山に据えられた。)や天水桶などの文化財、銭形平次の碑(銭形の平次は野村胡堂の名作「銭形平次捕物控」の主人公。平次の住居は、明神下の元の台所町ということになっている。此の碑は、昭和45年12月有志の作家と出版社とが発起人となり、縁りの明神下を見下ろす地に建立された。石造り寛永通宝の銭形の中央には平次の碑、その右側に八五郎、通称「がらっ八」の小さな碑が建てられた)、国学発祥の地碑、明治天皇御臨幸記念碑など
大公孫樹:江戸の昔よりこの地に育った由緒ある樹木。大正時代、関東大震災により社殿をはじめ神社の諸施設がことごとく炎上し崩壊したなか、その焼け跡に唯一残されたのがこの公孫樹だった。震災で焼け残った公孫樹からひこばえが生え育ち、その後、昭和20年の東京大空襲による油脂焼夷弾が東京一帯を襲ったが、昭和9年建立の鉄骨鉄筋コンクリート造・総漆塗の社殿は当時としては日本初の耐火耐震構造を持つ神社建築であったため焼失を免れた(国登録文化財・文化庁)。その一方、ひこばえは被災の憂き目にあったにもかかわらず立派な樹木となり親木を支えることとなった。親木のほうは枯木につき倒木危険防止のため上部を伐採して保存されている。江戸時代、月見の名所に植えられた公孫樹は、大正・昭和の災害にも遭遇しながらも子孫を残し、この地の歴史を伝えてきた大切なご神木と言える。災難除け・厄除け・縁結びのご神徳を持ち長い間この地を見守ってきたご神木として、今後も後世に伝えていく。ひこばえの生育が後世までも受け継がれてゆくことも心より願うものである。
《摂社》
★江戸神社(三天王 一の宮)
御祭神:建速須佐之男命/祭礼日:5月14日
大寶2年(702)武蔵国豊嶋郡江戸の地(今の皇居の内)に創建された大江戸最古の地主の神。古くは江戸大明神あるいは江戸の天王と称された。
鎌倉時代には、江戸氏の氏神として崇敬され、その後江戸氏が多摩郡喜多見村に移住の後、太田道灌築城してより、上杉氏・北条氏等引き続き城地に祀ったが慶長8年(1603)江戸城の拡張により、神田神社と共に神田台に遷り、更に元和2年(1616)に当地に遷座された。
江戸時代中期以後は牛頭天王と称され、明治元年(1868)に須賀神社と改称、更に明治18年(1885)に江戸神社と復称された。
この神社は、江戸開府の頃幕府の食を賄う菜市が開かれその後、貞享年間(1684〜)に神田多町一帯に青物商が相集い市場の形態が整った。こうした発祥の頃から市場の守護神として崇敬されてきた。
現社殿は平成元年神田市場が大田区東海の地に移転するにあたり江戸神社奉賛会の人々により今上陛下御即位大礼の記念として、大神輿を御神座として再建鎮座された。
…三山王祭・一の宮江戸神社の祭について
慶長18年(1613)より始まったと伝えられる神輿の神幸は6月7日の朝、明神の境内を発輿して南伝馬町二丁目に設けられた御仮屋に入り、氏子の町々を渡御して14日還輿された。その神幸の様は実に勇壮厳粛な行列であったと伝えられる。
現存する大神輿は、日本有数の華麗にして巨大な神輿で、通称「千貫神輿」として人々に親しまれ、神田祭に担がれる凡そ二百基の神輿の象徴でもある。
★大伝馬町八雲神社(三天王 二の宮)
御祭神:建速須佐之男命/祭礼日:6月5日
この神社は江戸時代以前に祀られていたと伝えられる。三天王の二の宮の天王祭は、6月5日明神境内を発輿し、氏子中を神幸し大伝馬町の御仮屋へ渡御して八日に還輿していた。このことから大伝馬町天王と称されていた。この祭は元和元年(1615)頃より行われて、江戸時代には他の天王祭と共に大変な賑わいの一つであった。今日でも大伝馬町一丁目・本町三丁目東町会の有志諌鼓会(神田祭の一番山車大伝馬町諌鼓山車より命名)の人々の篤いご信仰がある。
尚、東京の風物詩「べったら市」も神田神社兼務社日本橋宝田恵比寿神社で諌鼓会の人々により祭礼伝統文化行事として継承されている。
★小舟町八雲神社(三天王 三の宮)
御祭神:建速須佐之男命/祭礼日:6月6日
この神社は江戸城内吹上御苑より神田神社と共にこの地に遷座された。小舟町「貞享年間(1684〜)までは小伝馬町」お仮屋を有し神輿が渡御されたことから小舟町の天王と称された。
明治以前は公命により、江戸全町域の疫病退散の為、江戸城内・北奉行所・日本橋々上に神輿を奉安し祈祷が行われた。
東都歳時記によれば、当時の天王祭は一丁目にお仮屋ができ大提灯・大注連縄が張られ、二丁目には七、八間の絹張りの神門が造られその左右に樽積みが高々と重ねられた。三丁目には須佐之男命と稲田姫の造り物、八岐大蛇の行灯、天王祭の大幟をたて神輿の神幸を待った。
神輿は6月10日に明神境内を発輿して氏子百八十か町を巡り還輿するのは十三日か十四日その間の里程は十三里に及んだといわれる。このことから十三里天王ともいわれた。
近年では、八雲祭と改められ小舟町街中に壮大なお仮屋がたてられ、華麗にして勇壮な大神輿の神幸祭が不定期に斎行されている。
《末社》
★魚河岸水神社
御祭神:弥都波能売命/祭礼日:5月5日
日本橋魚河岸水神社は、徳川家の武運長久と併せて大漁安全を祈願する為、魚河岸の先人により武蔵国豊嶋郡柴崎村神田神社境内(今の千代田区大手町)に鎮座された。
元和年間(1615〜)神田神社と共に此の地に遷り、大市場交易神と称されその後、水神社と改称し更に明治24年(1891)魚河岸水神社と社名を変更し、日本橋魚市場の守護神として崇敬されている。なお、日本橋より築地に移った築地中央卸売市場内には、当社の遥拝所が建てられ、市場に関わる人々の篤い信仰により支えられている。
当神社の崇敬体「魚河岸会」の所有する加茂能人形山車は、江戸城内に参内し徳川歴代将軍の上覧に浴し、再三褒賞を賜った江戸の代表的山車であったが惜しくも関東大震災により烏有に帰した。
その後、昭和30年江戸文化の一端を永く後世に遺す為、文久2年(1862)当時そのままの山車を再現した。隔年に行われる神田祭には、その絢爛豪華な山車の全容を拝観することができる。
★末廣稲荷神社
御祭神:宇迦之御魂神/祭礼日:3月午の日
当地御創建の年代は不詳だが、元和2年(1616)頃のもので、極めて古い神社。
昔より、庶民信仰が篤く、霊験あらたかな出世井稲荷さまとして尊崇されている。現社殿は、昭和41年2月28日に東京鰹節類卸商組合の有志により再建された。
★浦安稲荷神社
御祭神:宇迦之御魂神/祭礼日:3月午の日
この神社は、往古江戸平川の河口に近き一漁村の住民により祀られ、天正年間(1573〜)徳川家康公江戸入府に当り城下町整備に際し鎌倉町の成立と共にその守護神として勧請された。寛政9年(1797)同町の崇敬の念篤き大工職平蔵により、社殿が造営され、爾来、浦安稲荷社として伝えられている。
その後天保14年(1843)8月、町割改めに際し神田明神社境内に遷座、さらに明治維新及びその後の戦火災に依り復興できぬ内神田稲荷社五社を合祀し今日に至っている。
★三宿稲荷神社・金刀比羅神社
[三宿稲荷神社]
御祭神:宇迦之御魂神/祭礼日:10月初旬
創建の年は不詳。江戸時代より神田三河町二丁目(他に皆川町・蝋燭町・旭町の一部が合祀され、昭和十年に司町一丁目に改称。更に昭和41年より住居表示に関する法律により、内神田一、二丁目の一部に編入され、内神田司一会となる)の守護神として奉斎されていた。その後当社12代神主芝崎美作守の邸内に祀られていた内山稲荷と合祀され、当社の末社として奉斎された。現在の社殿は、昭和41年10月7日に再建され、金刀比羅大神と共にご鎮座された。
[金刀比羅神社]
御祭神:大物主命・金山彦命・天御中主命/ 祭礼日:10月10日
天明3年(1783)に、武蔵国豊島郡薬研堀(現在の東日本橋二丁目旧両国町会)に創建された。江戸時代には、神祇伯白川家の配下となり、祭祀が斎行されていたが、明治6年(1873)7月に村社に定められた。
往古は、隅田川往来の船人達の守護神として崇敬され、その後、町の発展と共に商家、特に飲食業、遊芸を職とする人々の篤い信仰を集めている。
昭和41年10月7日、宗教法人を解散して氏神のこの地に建立し、三宿稲荷大神と共にご鎮座された。
★合祀殿:江戸時代に勧請された神々。関東大震災・戦災により社殿を焼失し、以来神田神社の本殿を仮御座として奉斎されてきた。「平成の御造替事業」の締め括りに、以下七社の御神霊を奉鎮する「合祀殿」として新たに御造営された。平成24年11月24日建立・遷座
・籠祖神社
御祭神:猿田彦神・塩土老翁神/御神徳:導きの神・海上安全の神・籠造り職人始祖の神/御由緒:寛政7年(1795)亀井町(日本橋小伝馬町周辺)の籠職人たちによりお祀りされた。塩土老翁神は、山幸彦(神武天皇の祖父)に竹籠の船を与えた神で、そこから籠職人たちに崇敬されたのであろう。現在も籠祖神講の人々により祭祀が行われている。
・八幡神社
御祭神:誉田別命(応神天皇)/御神徳:必勝祈願・心願成就の神/御由緒:江戸幕府が崇敬した境内の旧社で、連雀町(神田須田町・淡路町周辺)の町人によりお祀りされた。八幡神は武の神として有名で、源頼朝や徳川家康など歴代の武将が崇敬したため、全国各地にお祀りされている。
・富士神社
御祭神:木花咲耶姫命/御神徳:安産・子育て守護・火難消除の神/御由緒:文化12年(1815)神田漆師町(鍛冶町周辺)の町人によりお祀りされた。富士山に祀られた神で、海幸彦・山幸彦の母神様御神名は「桜や梅の花が咲くように美しい女性」を意味する。
・天神社
御祭神:菅原道真命・柿本人麻呂命/御神徳:詩歌・文筆・学問の神/御由緒:菅原道真公は、平安時代の貴族で、右大臣や太政大臣を歴任し政治家としての手腕を発揮する傍ら、学者・詩人としても優れていたことから、学問の神様として崇敬された。柿本人麻呂公は享保年間(1716〜)に、「江戸砂子」の筆者・菊岡沾凉により御神像がお祀りされた。柿本人麻呂は飛鳥時代の歌人で歌聖と呼ばれ36歌仙の一人であります。このたび詩歌に秀でた両祭神を合祀し、天神社として、勧請した。
・大鳥神社
御祭神:日本武尊/御神徳:開運招福・国土安穏・文武の神/御由緒:文政年間(1818〜)に社殿が建立され、柿本人麻呂命の神像と共に合祀勧請されたと伝えられている。日本武尊は国内を東奔西走し、大和朝廷の統一に貢献された日本の英雄神。各地の大鳥神社は、おとりさまと親しまれ、11月酉の日には、酉の市が行われている。
・天祖神社
御祭神:天照大神/御神徳:日本の総氏神・皇祖の神/御由緒:古来より神社境内にお祀りされ、湯島横町の町人により崇敬されていた。天照大御神は、伊勢神宮のご祭神で、皇室の祖神であるとともに日本の総氏神でもある。全国的に天祖神社・神明宮としてお祀りされている。
・諏訪神社
御祭神:建御名方命/御神徳:五穀豊穣・交通安全・開運長寿の神/御由緒:古来より此の地にお祀りされていたが、享和2年(1802)日本橋本町三峰講中により社殿が造営されお祀りされた。建御名方神は、神田神社の一の宮御祭神大己貴命の御子で、大己貴命とともに葦原中津国を治めた武勇の神様。

![MAIN PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda1.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda2.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda3.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda4.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda5.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda6.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda7.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda8.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda9.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda10.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda11.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda12.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda13.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda14.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda15.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda16.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda17.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda18.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda19.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda20.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda21.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda22.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda23.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda24.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda25.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda26.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda27.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda28.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda29.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda29-2.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda30.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda31.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda32.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda33.jpg)
![OTHER PHOTO:神田明神[神田神社]](https://shrine.iki-kiru.com/wp/wp-content/uploads/kanda34.jpg)
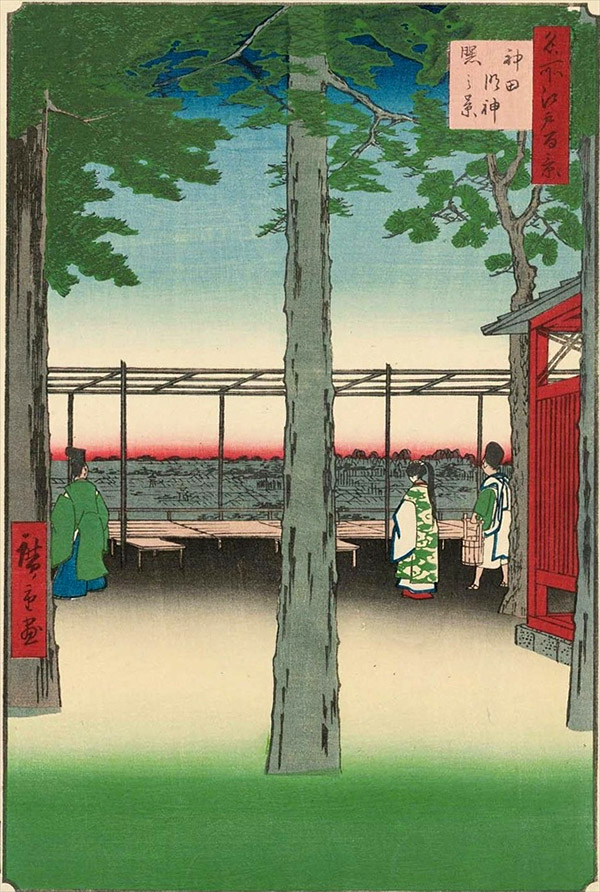
コメントを残す